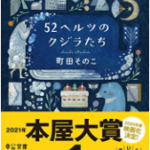感想:仕事と家族 日本はなぜ働きづらく、産みにくいのか
★★★★☆
同著の感想:結婚と家族のこれから~共働き社会の限界~とセットで紹介されているのを見かけてたので、セットで読んでみた。20代、30代世代に焦点を当てて、今の日本の、仕事・家族の当たり方について、前著では、家族によりフォーカスを当てて、本作は仕事によりフォーカスを当てた内容になっていた。被る部分もあるが、僕もセットで読むのをおすすめする。
女性の労働参加率と出生率が正の相関を持つことが必須
このように女性の労働を「結婚生活を妨げるもの」ではなく「結婚生活を成り立たしめるもの」として捉えるようになるという転換は、他の国も一定の時期に経験してきたものだと私は考える。このような状態になると、女性の就労は結婚を遅らせ出生率を下げるというよりも、むしろ結婚に必要な要素として考えられるようになる。
これからの社会で一番必要になってくるだろうと思われること。政府の大小を抜きに考えると、スウェーデンやアメリカも、過去には今の日本のような女性活躍問題を抱えていたが、今では乗り越え、女性の労働参加と出生率が正の相関を持つようにまで至っているようだ。
そのための今ある壁をして、男社会の無限定性な働き方を著者は指摘している。
正社員の働き方の「無限定性」 日本企業の基幹労働力として採用された者は、仕事に関する三つの「無限定性」を受け入れることを要請される。職務内容の無限定性、勤務地の無限定性、そして労働時間の無限定性である。
高度経済成長時の専業主婦がいる家族のモデルケースがあったからこそ、成り立っていた無限定性な働き方だが、若手サラリーマンだが、今も問答無用で無限定性は求められている。面白いことで、一番問題なことが、出産した女性だけが政府の強い後押しがあって解除される傾向にあるということ。結局パートナーである男性が無限定性を求められると、今がないということにどれだけの人が気づいているのか。待機児童問題や、育休など子供を育てられる制度を用意するのに躍起になっているが、問題の本質が見えてきて、真の意味での女性活躍や、共働き夫婦が子育てと仕事を両立できる社会はいつやってくるのだろうか。間違いなく今は過渡期で、その真っ只中に子育てをすることになるだろう自分にとっては頭が痛い…。
少子高齢化、地球温暖化、etc…50年スパンのディレイがある問題を取り組むことは本質的に怠け者の人にとってそもそも不可能なのではないか、と考えさせられる。
ひとりひとりにあった働き方を。(なんか安倍さんがいってたような)
そんな夢のような社会が来ることを祈る。
スポンサーリンク
スポンサーリンク
関連記事
-
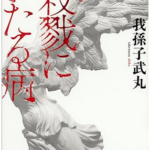
-
感想:殺戮にいたる病
著者:我孫子武丸 ★★★★☆ たまたま見たひろゆき切り抜きYoutubeでひろゆ …
-
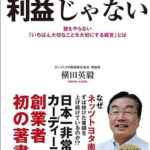
-
感想:会社の目的は利益じゃない ―――誰もやらない「いちばん大切なことを大切にする経営」とは
著者:横田英毅 ★★★★☆ 「あなたにとって一番大切なものはなんですか?」 「そ …
-
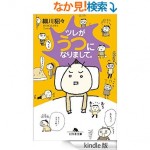
-
鬱のことが分かりやすい漫画『ツレがうつになりまして。』
著者:細川貂々 ★★☆☆☆ 何も考えずセールなのでポチってた。読んで初めて漫画だ …
-
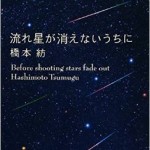
-
感想:流れ星が消えないうちに
著者:橋本 紡 ★★☆☆☆ 久々に本屋をぶらぶらしていたら懐かしい著者の名前を …
-
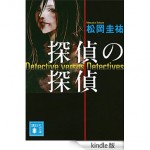
-
感想:探偵の探偵(小説)
2015年7月から北川景子主演でドラマ化されることを,読み終えてから気づきました …
-
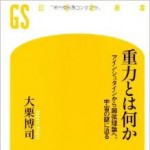
-
『重力とは何か』ニュートン,アインシュンタイン,量子力学と物理学の歴史をわかりやすく紹介している良書でもあった
インターステラーという映画内で,重力の謎が解ければ,宇宙の真理を理解でき,地球か …
-

-
感想:運転者
著者:喜多川 泰 ★★★★☆ 小説と思ってたら小説風のストーリー仕立ての自己啓発 …
-
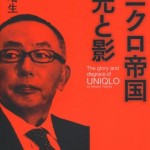
-
感想:ユニクロ帝国の光と影
著者:横田 増生 ★★★☆☆ 山口の田舎の呉服やから世界のユニクロまで成長させた …
-
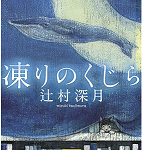
-
感想:凍りのくじら
著者:辻村 深月 ★★★☆☆ ラノベばっかり読んでる時に、普通の小説も読みたいな …
- PREV
- 液体窒素によるイボ治療日記1
- NEXT
- 感想:「育休世代」のジレンマ~女性活用はなぜ失敗するのか?~